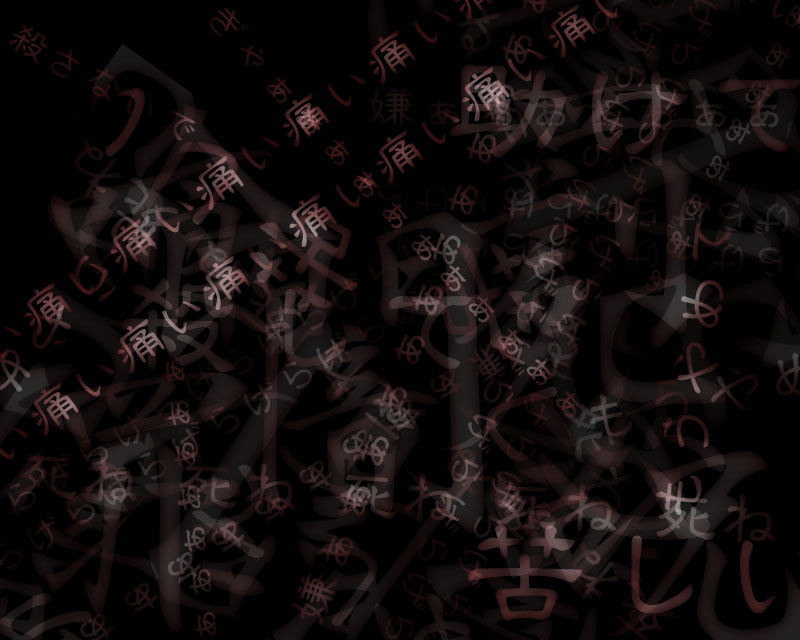
第漆章/無明長夜
8
「ごほっ……」
肺が酸素の代わりに闇を吸う。哀は気管を腐らせる瘴気にむせび、今日何度目かの喀血を、袖口でぬぐった。
封印を行うには闇の中心地まで潜行しなければならないが、最低限の結界で呼吸を確保していれば、からみついた亡者の腕がそこまで運んでいってくれる。
哀は浅い呼吸を続け、封印の刻を待っていた。
それは時代の波に消えゆく鬼遣たちが編み出した、最後にして最大の秘儀。
羅刹鬼を孕んだ憑坐をただ殺すのではなく、神剣と融合させ、その神力と魂を礎に羅刹鬼を永遠に幽界に楔留める、名も無き究極の封印法術。
老人は哀にその秘儀を託し、鬼遣の里は彼女を除いて全滅した。だが、哀は老人たちの無念の思いを裏切るつもりだった。謀反と言ってもいい。
憑坐ではなく自分の身体を使って封印を行う。もう妹を犠牲にするつもりはない。
だが、それを老人に言えば哀は殺され、転生した赤子に再教育を施しただろう。
しかし哀の考えた方法はまったくの無茶というわけでもなかった。むしろ成功する確率の方が高いのだ。不確定要素は多いが、やってできないことはない。
一方で、そのための仕様ではない身体で行なおうとしていることも確かだった。“鬼遣”の身で封印を執り行えばどうなるか───哀にも大方の予想はついた。
元は“憑坐”と同じ物からできているのだ、羅刹鬼を納められないと言うことはない。
ただし、その時の自らの姿は形容しがたいほどの醜(しこ)めし様となっているだろう。
この無限に近い闇を胎内に納めたならば、子宮は風船のように膨れあがり、臓器が順番に破裂していく。あとは封印が先か七孔憤血が先か。さながら真空に投げ入れられた蟾蜍だ。
「けれど……」
哀は思う。無惨な死に方に恐れはない。これが罰なのだとすれば、それこそが千年もののあいだ漫然と罪を犯し続けてきた自分を許してくれる唯一の救済(すくい)かもしれないのだから。
ごぼん、と重い泡音を立てて、海流が止まった。
絡みついた闇の手が離れていく。どうやら羅刹鬼の中枢にたどり着いたようだ。
───さあ、もう時間がない。始めよう。
哀はそう心に決めると、最低限の結界も解いた。入り込んできた闇の海水が全身を包むと、五感が鈍化し、五感以外の感覚が鋭敏になる。
そうして感じえるは、負の刺激。孤独、不安、絶望。他人の怨念が肌を這うこのおぞましさ。どうしても慣れることのないものたち。
この虚海にはそれらが蔓延している。光を喰らう闇はあらゆる負を内包している。
神剣の力が落ちていくのが、支えている腕の疲労から分かった。闇は神剣の弱光すらも食いつぶし、光の源たる我が身に侵入してこようとする。
闇に喰い破られる、それ自体に痛みはない。だが、甘いような苦いような、自分が自分以外の何かになっていく感覚が、どうしようもなく怖い。
その恐怖もいずれは消える。今この時が、千年ものあいだ待ち焦がれていた瞬間だった。
死を夢観て今まで戦ってきた。羅刹鬼を殺せば死ぬことができる。この苦痛だらけの生を終わらせることができる。
死による解放(やすらぎ)を。それだけを切に願って戦ってきた。はずなのに、今は───、
「…………死にたく、ない……」
哀は漏れたつぶやきを理解したくなかった。それは思考ではなく、想いからあふれた言葉だから。故に理解してしまえば、彼女はもう“鬼遣”ではいられなくなる。
死にたくない───千年の中で、哀は初めてそう思った。死への恐怖。何故そんなものを感じるようになってしまったのか。
決まっている。彼と出逢ってしまったからだ。
京平と生きたい。一緒にいたい。その想いが、死を安息から恐怖に変えてしまった。
それは誰もが感じる想い。誰もが知る、死ぬことの怖さ。哀はようやくそれを知った。
そして、知ったときには、もう遅い。
死はすでに彼女の大半を蝕んでいる。生き延びることなど、もはや叶わぬ夢なのだ。
大人しく闇を子宮におさめ、神剣で腹をかっさばく。たったそれだけのことなのに、どうしてこの腕は動いてくれないのか。どうして独りで死ぬのはこんなにも惨めでせつないのか。
「死にたくない……………死にたくない………死にたくない、死にたくないっ!」
うったえは誰にも届かず、廣(ひろ)すぎる闇はその声を木霊させることも許してくれない。
叫んだせいで気管が裂けた。咳き込み、哀は何度も血を吐いた。
───分かってる。そんな身勝手が許されるはずがない。
最初からこの結末を予期していた。望んでさえいたはずだ。
そう、本当に怖いのは死ぬことじゃない。
「……………あなたは、生きて……」
誰彼にも届かぬ言葉を哀はつぶやき、封印の議を執りおこなった。
薄く目を閉じ、神剣の刃に手を添えて、水平に掲げる。ささやくように呪の詩を詠み上げると、刀身から虹色の光が漏れ始めた。
七燿の光波は周囲に停滞し、哀を取り巻く巨大で複雑な紋様を築きあげる。平面の紋様は層を重ねて立体化していき、まるで綴れ織る錦のように彼女を包み込んでいく。
自ら生み出した力場に共鳴し、激しく振動し始める神剣。哀はそれを細心の注意を払って制御する。振動はやがて収束し、神剣は滞りなく楔としての機能を発現した。
次は依代の準備だ。いよいよ闇をその身に収める時が来た。
深呼吸したかったが、腐った肺でそれをやれば、たぶん封印する前に死ぬ。
哀は第六感の範疇にある咒力を集中させ、闇を隔絶する最後の堰杭(いぐい)を外した。結界が消え、堰き止められていた闇が大量に流れ込んでくる。
それは映像であり、触れ得るものであり、耳を聾(ろう)する亡者の叫びだった。
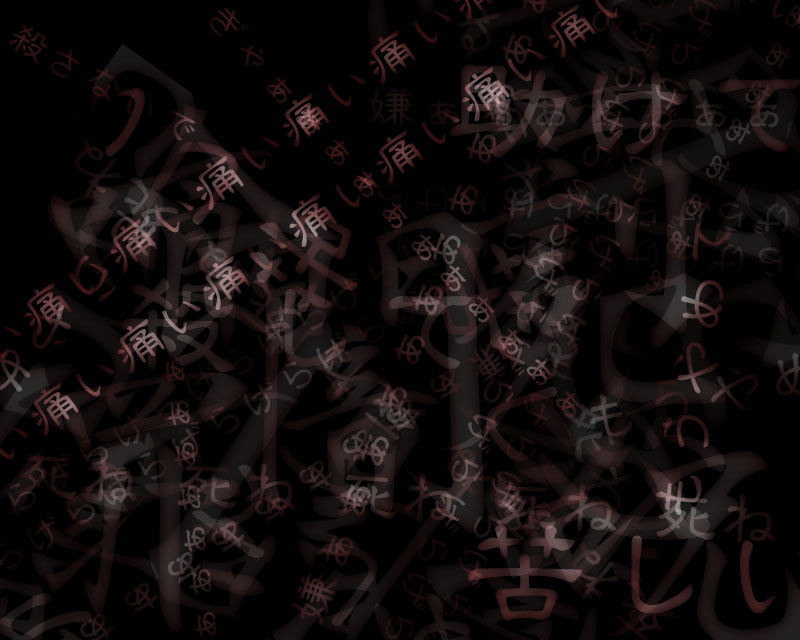
悲鳴。断末魔。そしり。怒号。哀願。怨詛───脳を灼く憎炎の渦。
「………ぅあ……ァ……っ……ぁぁぁっ……」
これが羅刹鬼を構成している物だというのか。脳を破壊する多量の情報が闇もろともに押し寄せてくる。魂が汚染され、心身が陵辱される。
もう戻る道はない。母胎を見つけた闇はその存在を収めきるまで侵食をやめないだろう。そして侵食が終わったとき“阿防羅刹鬼”は“鬼遣”の仔(こ)となる。そのときが、仔を決して産まれぬ仔とする封印の瞬間だ。
封印が完了すれば、おそらく何を考えることも、何を感じることもできなくなるだろう。存在に必要のないものは全て切除されて、ただの単細胞生物に成り下がる。知性や感情、記憶や心。そういったものが一番無駄だ。
人の精神で永遠の刻に耐えることはできない。五感を排斥し、思考を鈍化させなければ、貧弱な魂は百年と経たずに発狂し、今度は哀自身が新たな破壊神として世界に滅びをもたらすことになるだろう。
それは封印を永遠のものとする上で、必要不可欠なことなのかも知れない。
けれど、そうなれば京平のことも忘れてしまう。それが哀の残した唯一の未練だった。
憶えていたい。忘れたくない。彼といたわずかな時間だけが、自分の生きていた瞬間だった。
殺すことしか知らない自分に、彼は優しさを与えてくれた。泣くことすら忘れていた私に、彼は感情を思い出させてくれた。人と接したこともない私に、彼は人を好きになる気持ちを教えてくれた。
すべては走馬燈のように流れ、心の大事なところで揺蕩(たゆた)っている。
それが一つ、また一つ、記憶から抜け落ちていく。
貪られ、ついばまれて、無くなっていく。
消えてしまう。伊月哀ではなくなってしまう。自我の消失。まるで溶けていくような終焉。
消える。姿が、思考が、感覚が、心が、記憶が、───自分が。
闇が降りて、光を忘れて、虚無の恐ろしさだけに満たされていく。
音叉のように高く鳴り喚く神剣の切っ先が下腹に触れる。
「……………京……────」
そして、ぶつりと意識がとぎれた。