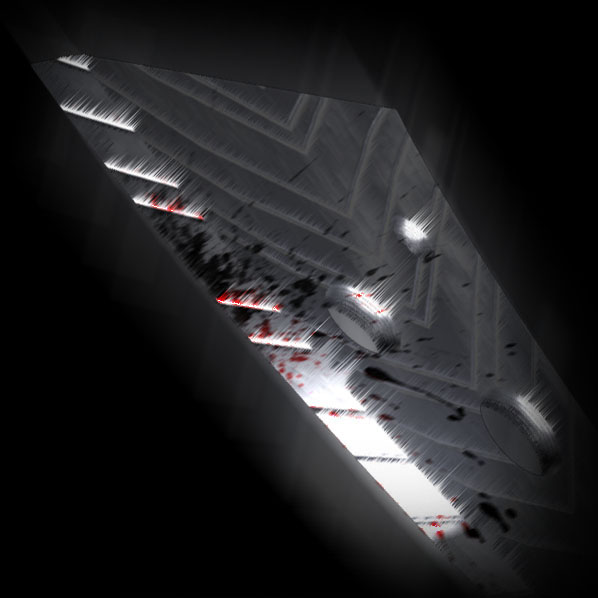
第陸章/蒼茫の傷痕、澱む流砂
5
おはよう、京平。
今は夜ですか。朝ですか。外は晴れていますか。それとも曇っていますか。
もし雨が降っているのなら、あなたの妹はきっと無事です。
あなたを狂わす元凶も消えているはずです。
私にはそれを確かめるすべはないけれど、すべては上手くいったと、そう思うことにします。
自分のしたことが無意味だったとは、思いたくないから。
真実を知った時、京平はもしかしたら自分を責めるかも知れません。
けれど、それは違います。
すべては私の過ちから始まったこと。誰も悪くない。ただ、私だけが罪を犯した。
罪の上にまた罪を塗り重ねることでしか、私には生きる価値がないようです。
いえ、もはや死ぬ価値もない。
それでも、最後は自分の意志で戦ってみようと思います。使命や義務などではなく、自分自身の意志で。
そう思えるようになったのは、他でもない、あなたがいてくれたから。
こんなことを言うと怒りますか?
怒るのでしょうね。あなたは優しいから。
あなたのその優しさに触れることができて嬉しかった。
泣くことも、笑うことも、あなたが思い出させてくれた。本当に嬉しかった。
でも今は、それがつらい。
私のしてきたことを知れば、京平は決して私を許さないと思う。
だから、一人で行くことにします。あなたにだけは知られたくないから。
何があっても、どうか自分を責めないで。なにもかも私が悪いのだから。
好きです。それから、さようなら。
──────────────────────────伊月 哀より
† † †
手紙の最後に書かれた名前は『海神』ではなく『伊月』とあった。書き慣れないその字はひどく乱れていた。
それが彼女にとっての運命へのあらがいになるのか。こんなささやかなことが反抗だというのか。
「クソ……っ!」
怒りにまかせて速度を上げる。だが鋼の自重が枷(かせ)となってその足取りはどうしようもなく重い。
全身の関節が軋んで、ろくに走ることもできない。
見た目こそは鬼の形姿(なりすがた)を保てているが、中身は人間以下だ。超常の力がまったく出せない。それどころか身体の動かし方すら忘れてしまっている。
「っ……はぁっ……はぁっ……!」
広い道路に出た。息を荒くつき、膝に手をついて視界をめぐらす。だが哀の姿は見えない。何も告げずに出て行った彼女の行き先など、皆目見当がつかなかった。
「っ………なんでだよ……。なんだよ価値って? 好きだって理由じゃ駄目なのか?」
結局、自分は哀を変えることが出来なかった。あの約束が偽りだったとは思わない。けれど彼女はしがらみを選んだ。
「ひとりで背負(しょ)いこんで、勝手にあきらめて、自分犠牲にして他のヤツ助けて。それで満足かよっ……!」
深閑の街に、その声を聞き咎める者はいない。彼女はどこにも居ない。
「もっと欲張ったって良いじゃねェか。そんな簡単に捨てるなよ……!」
重い傷を負ってからも無理を続けていた哀がまともに戦えるはずがない。あんな身体で出歩けば、たちまち鬼の餌食になってしまう。
だが彼女の姿は一向に見つからず、恐慌が胸を蝕んでいくばかり。
正午をすぎたばかりだというのに外は真っ暗だった。太陽は分厚い暗雲に遮られ、彼女と同じようにその姿を隠してしまっている。
いくら探しても哀はどこにもいなかった。しかし超常の力が使えなくなった今、こうして足を頼りに探し回ることぐらいしか彼女を見つける方法を思いつかない。
急げ。ひどく胸騒ぎがする。
ひたすら走り続けて、角を曲がったときだった。
「………ッ!」
目の端が何かを捕らえた。高速で接近してくるそれは探し人ではなく、“岩”だった。
「がっ……?」
岩塊が真横から直撃する。とっさに身をよじったものの、大型トラックの突進にも匹敵する衝撃にあやうく意識が飛びかける。
しかし予想に反して京平の身体はさしてダメージを受けていなかった。
ほとんどの能力を失ったが、防御力だけは健在だったらしい。鋼で覆われた頑丈な皮膚に感謝して───いる場合ではない。いまだ自分は吹き飛ばされている最中だ。
無防備な体勢から撃ち倒された京平は、錐揉みしながら地面をバウンドする。大地に遍く慣性の法則が滑走を永続させ、火花と白煙が盛大に散り敷いた。
「が・あ・あ・あ・ぁ・ぁ・ぁ・ぁっ……!」
ヤスリに等しいアスファルトに背中を刮がれ、京平は絶叫をあげた。灼け付くような摩擦の激痛を堪えて何とか逃(のが)れようとするも、“岩”がのしかかっていて身動きが取れない。
いや、陰惨な笑みを浮かべたこれは岩などではなく───
「死ネ死ネ死ネ死ね死ネ死ね死ネぇぇゥゥゥっ!」
───醜悪な鬼。
豪腕が首を押さえつけ、そこへもう一方の鉄腕が振り落ちてくる。
鉄塊から削りだした巨大な鉞が、闇を薙ぎながら京平の眼前に迫る……!
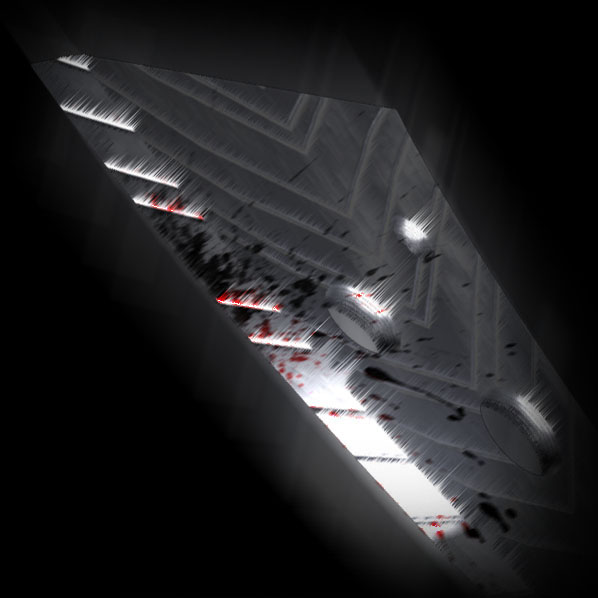
「っ! オラァっ!」
あわや頭蓋が真っ二つというところで、鉞の横腹を殴りつけることに成功した。
非力な拳撃でなんとか軌道をそらすも、肉厚な刃が左肩をかすめ、砕けたアスファルトの破片が京平の頬を浅く裂いた。
「こっ、の……、暑苦しいんだよブタがっ!」
急所に蹴りを入れ、ひるんだところを脱出する。
身を丸めて路上を転がり、勢いがゆるんだところで両手で地面にしがみつく。金属の指が硬いアスファルトに轍(わだち)を刻んでいき、足も使ってブレーキをかけると、ゴムの焼ける匂い。靴底が剥げたようだ。
土煙が夜気にただよう。冷や汗が胸を伝って落ちた。左肩がずきずきと痛む───肉を少し持っていかれた。
「………野郎」
裂けた頬をぬぐって、京平は敵の姿を睨みつけた。
「ブふっフヘへ……」
不気味な笑みを浮かべるこの鬼には見覚えがあった。
「テメェは───」
「ボクのウデ、返しテよ。ねエ、返シてよ」
嗅鼻はだだっ子のように訴え、達磨(だるま)のような身体を揺すりながら、つたない足取りでよちよちと歩いてくる。
だが、ねじくれた巨木のような片腕を地面に着いた瞬間、その手で地面を“蹴り”、恐ろしいまでの加速力で肉薄してくる。
「───ッッ?!」
爆ぜるような斧音(おのと)。とっさに受けた金属質の腕が裂けた。続いてふんばっていた足が持ち上がり、吹き飛ばされる。
後方に民家が迫った。京平は向きを変えることも出来ず、後頭部から民家に突っ込む。
すんでの所で頭をかばうも、衝撃はブロック塀を破壊し、窓ガラスを砕き、フローリングの床や家具を木と鉄屑に変えていく。
貫通。爆砕。倒壊。そしてまた貫通。次々と民家を突き破り、なおも衝撃は続く。
住民は無事だろうか。あちこちに痛みを覚えながら京平はそんなことを考えた。
二件の家屋を半壊させて、ようやっと止まる。
「っ……なんつー馬鹿力だ……」
漆喰の壁を蹴りのけて、瓦礫に埋もれた身を起こす。
奴のこの攻撃力。こちらの力が落ちているのとは関係なく強い。鋼を鎧(よろ)うこの身体でなかったら、今ごろは木端微塵にされているところだ。
京平は耳鳴りのする頭を振って土埃を落とす。ボロ切れになった学ランを脱ぎ捨てようかどうか迷っていると、人影が見えた。
敵? 鬼か?
違う、人だ。
この家の住人だろう。早くこの場を離(はな)れなければ、あの鬼が来てしまう。
京平はそう判断し、住人に注意をうながした。
「危ないぞ。下がってろ──」
返事は包丁の閃きで返された。
「っ?!」
とっさに右へ躱す。みっともないぐらいに動きが鈍っていた。
「やめろ! 俺は敵じゃない!」
「……………………」
包丁を手にしているのは、エプロン姿の主婦だった。
確かに今の京平は鬼に見えても仕方がない。なにせこの風体だ。
しかしだ。普通、化物を目の前にして戦おうとする人間がいるだろうか。それもただの主婦が。
「ウ、ウゥゥァァっ!」
獣のような雄叫び上げて主婦が飛びかかってくる。
「くっ!」
駄目だ。反撃すれば殺してしまう。この鋼の腕では気絶させるのは無理だ。
京平は逃走を選択し、自分で突き破った穴から外に出た。
そこには───人がいた。大勢の人が。
塾帰りの学生。スーツ姿のサラリーマン。幼稚園に向かう途中だったであろう園児。メイクが憤怒の形に滲んでしまっているOL。杖を武器にした老人───街に住むあらゆる老若男女。
総じて正気の顔色を欠失している。
そこへ、ずしりという着地音。あの鬼が追いついてきていた。
人々は嗅鼻の盾となるように京平の前に立ちはだかった。
「……………。……クソが……」
これでどういうことか分かった。
しかしこの鬼にそんな細かい芸当ができるとは思えない。他に仲間がいるはずだ。濃い線はあの痩せた鬼か。
だが嗅鼻の返答は、京平の予想とはまったく異なる答えだった。
「カカ、訶利帝母様ガ約束しテくれタンダ。見目を献上スレば君と戦わせテクれるって」
献上の意味するところは、つまり───
「仲間を、売りやがったのか……!?」
「? 何ヲ驚いテルんダイ? 良いじゃないカ、きみノ敵が減ったンダから。見目ノことは昔から気ニ入らなカッたンだ。アノ女、僕ノこと馬鹿だッテ思ってるんだよ。ヒドいヨね。ダカラ訶利帝母様にアゲたンだ。トテモすがすがシイ気分ダよ」
自慢気に話して、嗅鼻はニタニタと口端を拡げた。
「………どこまで腐った野郎だよ」
噛みしめた奥歯がぎしりと軋んだ。
すでに周りは一分の隙もないほどに人で埋め尽くされている。
鉄塊の厚刃が重い音を立てて太い肩に担がれた。
「────ィィィィィィィィィィィィィィィィィいいいいいいいいいいいいいいいい行くよぉぉぉぉぉぉぉぉぉォォォォォォォォォッッ!!!」
嗅鼻が咆号した。今は敵となった人々が殺到してくる。
そして、狩りが始まった。