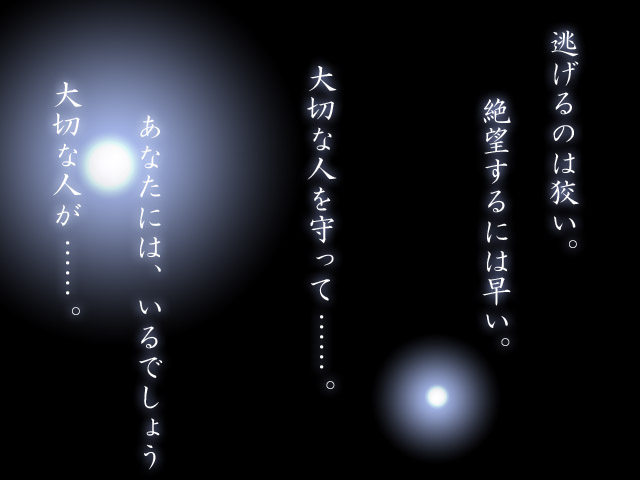
第肆章/紅藍の霞、罹る朧月
2
見目たちがいなくなると、数里に渡る空間のずれが復元され始めた。強制的に歪められた空間が揺り戻しによって大きく波打つ。
結界が解けたばかりでまだ辺りに人気(ひとけ)は無いが、この惨状を誰かが発見すれば、すぐに騒ぎが起きるだろう。
街に物怪(もののけ)の匂いが染みつく前に、哀は“雨乞(あまごい)”を始めた。
鞘に収めた刀を恭しく天に拝して、天紡ぐ五龍に祝詞(のりと)を捧げる。
すると幾分も待たずして、ぽつぽつと粒の小さい滴が降り始めた。それはじきに大地を洗う涼雨となるだろう。
魔物の腐った血肉を昇華させる法術の雨。この雨が降る限り、鬼共はなりを潜めて出てこない。
「すぅ…………は……」
哀は覚悟を決めたように息を整え、大きく穿たれたクレーターへと降りた。
大穴の中央には、意識を失った京平が横たわっている。
身体に目立った外傷はない。すでに修復してしまったのだろう。ただ鬼と言うだけでこうはいかない。凄まじいまでの治癒能力だった。
気を失っても京平は人の姿に戻ろうとしない。刃金(はがね)と化した腕が雨に濡れて鈍い輝きを放っている。
哀はひざまずくと、京平の頭を抱き起こした。
上唇からのぞく、小さいが確かにある牙。額には金属質の突起が二本、生えていた。
───もはや決定的に、彼は鬼だ。
「っ……グ……グルル……」
京平は苦しげに喉を鳴らして、焦点の定まらない片目を開けた。その虹彩は熾火のように燃えていた。
「……………約束……」
哀は小さくつぶやいた。
そう、約束を果たすときが来た。彼がどうにもならなくなったとき、止めるのは自分だと───そう約束した。
理性を無くした鬼は必ず人を襲う。そうなる前に始末しなければならない。
使い込んだ刀の柄(つか)は吸い付くように手の平に収まった。鯉口を切り、刀を引き抜く。
鞘を滑る刀が鈴の音を鳴らす───それは絶えず聞いてきた処刑の宣告。
逆手に持った刀を京平の首に押しあてる。容易に動脈を探り当て、血管の表面にまで刃を刺し入れる。
───最後の一押しは簡単だった。
………簡単だったはずだ。こうやって何年も、何十年も、何百年も、数多の鬼を屠ってきた。
彼を殺してもその数が一つ増えるだけだ。いまさら罪悪感など感じない。
「………だけど……」
刀を握る手は小刻みに震え、その先へ進むことが出来ない。
「………私は……」
彼を殺す───殺せるのか? 初めて自分を人として扱い、接してくれたこの少年を。
羨望すら覚えたあの暖かさを、危険というだけで消してしまっていいのか。
彼は自分の意志で鬼になったわけではない。羅刹鬼に無理やり目覚めさせられなければ、自分が鬼だと言うことも気づかずに一生を終えていただろう。
それをこんな風に、何も分からないうちに首を掻き切られて、彼は死ななければならないと言うのか。
───だとしても、殺さなければならないのだ。殺せなければならないのだ。自分が“鬼遣”と名乗るなら。
さあ、殺せ。彼もそれを望んでいたではないか。害を及ぼす前にさっさと駆除してしまえ。
冷徹な鬼遣としての思考が、すみやかな屠殺を要求する。
───殺す。彼を殺す。私は彼を殺す。
「…………私は……」
彼を────。
「わだ……つみ?」
呼び声は人の声をしていた。うなり声でも咆哮でもなく、それは確かに人の声をしていた。
「……………」
刃を握っていた手から力が抜ける。支えを失った刀が濡れた地に落ちた。
風失せた夜にさめざめと雨声がささめく。
「………お前、泣いてるのか?」
硬い金属の指が哀の頬に触れた。
降りそそぐ雨の中、それを確かめるすべはない。もし彼女が泣いているのなら、その理由は何なのだろう。
「海神?」
ふたたび忌名を呼ぶ少年の視界を、白い手が覆った。
触れるとそれだけで壊れてしまいそうなその手は、凶器にしかなり得ない。
けれど彼女の手は、えもいわれぬ優しさをともなって、京平の頭を包んでいく。
武器を扱うためだけに在った両手は、不器用に、慈しむように、初めて人を抱いた。
彼女の頬を伝う雫は幻だったのか。京平にはそれを確かめることはできなかった。それ以上彼女を見つめ続けることが叶わなかったから。
「泣いているのは、雨………」
雨は泣き続ける───涙を流せない少女の代わりに。
† † †
口に溜まった雨水を飲み干すと、乾涸らびた喉に無味の潤いがしみ渡った。渇きが癒されると、やがて意識がはっきりしてくる。
肌を打つ飛沫は、この世界が紛れもない現実であることを、しめやかに謳っていた。
───身体は………動く。
神経は………雨の冷たさが分かるならなんとかなるだろう。
すぐにでも楓呼を助けに行きたかった。なぜ妹ではなく俺が助かってしまったのか。何も出来ないまま、連れ去られてしまった妹。
奥歯が軋る。悔恨に負けないよう、自分に言い聞かせる。
───大丈夫だ。焦るな。楓呼は助ける。悪いのはあの鬼共だ。誰の所為でもない。
だから───憎しみを彼女にぶつけるのはやめろ。
「………なんでもっと早く来てくれなかった」
───我ながらなんて恨めしげな声なんだと思った。
そんな事を言いたいんじゃない。彼女が責められる謂われなどないんだ。
俺だって………いや、俺が助けてやらなきゃいけなかった。
───誓ったのに。責められるべきは俺なのに。
「なんで………、なんでもっと早くっ!」
けれども、出てくるのは口汚い罵りばかりで。
憤りの念が抑えられない。憎い。誰も彼もが。無力な自分が。
化物にさらわれた楓呼がこれからどういう目に遭うのか。それがよぎるだけで全身の毛が嚇怒に逆立つ。
なんで楓呼なんだ。妹に血のつながりはない。ただの人間だ。まだ十五の子供なんだ。
───殺してやる。あいつら全部。探し抜いて、見つけ出して、一匹残らず殺してやる………!!!
「ごめんなさい………」
唐突だった。
はっとして見上げる。どうして彼女が謝ったのか理解できなかった。
「あの娘を助けられなかったのは私のせい。好きなように誹(そし)っていい………。だから、どうか自分を追いつめないでほしい………。そんなことをすれば、あなたは本当に人間(ひと)ではなくなってしまう……」
「…………。海神………」
───後悔した。自分のことばかりを考えて彼女を傷付けた。この娘も楓呼と一つしか変わらない少女だったのだ。そんな子供に俺は何を押しつけようとしていたのか。
「……………すまん」
自分の馬鹿さ加減にほとほと呆れた。彼女には二人を助ける余裕はなかったのだ。
あの状況を見れば分かったはずだ。俺だけでも助けてもらったことを感謝すべきだった。
「………いいの。あなたは身体を休めていて……」
けれど彼女の気配は重く沈殿したままで、それは非難に傷ついたからではなく、彼女自身が言い拵えようとしている言葉のせいだった。
彼女は伏し目がちに、歯切れの悪い切り出し方をする。
「ここから先は私に任せればいい……。あなたの妹は必ず助ける……。だから……………」
「だから、『おまえは大人しく家で待っていろ』………か?」
柔らかな枕を離れ、顔を伏せたままの彼女を見つめる。
「………あなたは今とても不安定な状態にある。次に荒ぶれた時、理性が残っているとは限らない……」
「………。あんたには、感謝してるよ」
本当だ。感謝してる。仮借ない言葉で傷付けたことも謝りたい。
───だが、それとこれとは話が別だ。
「俺は待ってなんかいられない。楓呼は俺の妹なんだ。俺が助ける」
「無理。あなたは足手まといにしかならない」
彼女は膝にあった重みに代わるものを取った。鞘におさめ、腰に佩く。
「手伝ってくれとは言わない。………邪魔をするな」
「それはこちらの科白。見目や嗅鼻ごときにおくれを取るあなたが何の役に立つ……」
海神の動きに合わせて立ち上がり、その鋭い双眸を見据える。彼女の瞳には、金属の腕を持つ化け物が映っていた。
「負けやしねェ。ヤツらが鬼なら───俺もまた鬼だ」
異形の両拳を固く握りしめる。
「わかるんだ。この腕は何も産み出さない、破壊しかもたらさない。だけど、この腕なら楓呼を助けられる。この力、いま使わないでいつ使う?」
「永遠に使わなければいい」
彼女は無下に言い捨てた。
「………平行線だな」
説得は無理だとあきらめた。軽く息をつく。
「いいさ、勝手にやる。………俺はもういつ死んでも構わないんだ」
どのみち化物となった我が身では、人間の社会で生きていけない。それなら、最期に妹だけでも助けよう。そうすればこの汚い命も少しは救われる。
「そう………」
澄んだ声で彼女は答えた。そこには明白な殺意が混じっていて───
一瞬遅れてやってくる白刃の一閃。
血が蒼茫とした雨夜に舞った。紅く滴るそれは、雨と交わり大地へと流れる。
「……………。好きにしなさい……」
斑模様の緋刀は、首皮をかすめて止まっていた。
海神は円を描くように刀を鞘に納め、京平の脇を通り過ぎて去っていく。
これで完全に決別してしまった。彼女の協力も無しにどうやって楓呼を助けだそうか。
「ついてきて………」
その声が届いてくるかこないかの所で歩みを止めて、彼女は背中越しに言った。
「あなた一人を放置する方がよほど危険。無茶をしないと約束するのなら、行動を共にしても構わない………」
「いいのか………?!」
彼女は小さなうなずきを返して、また歩き出す。
「それから、二度と死ぬなんて言わないこと。………死にたがりは周りの人間まで巻き込む」
「………悪い」
「それに………」
そこから先はかすかなつぶやきだったが、ちゃんと耳に届いてきた。
「あなたが死ねば悲しむ者もいる………」
「? それって………」
聞き返そうかどうか迷ったが───結局聞こえなかったふりをした。
何となく、照れくさかった。
† † †
「で、これからどうするんだ?」
細い白雨を浴びながら、京平はたずねた。とりあえずあの場から離れること数分。二人とも頭のてっぺんから爪先までずぶれである。
「とりあえず、わたしの隠れ家に行く。たぶんそこが一番安全………」
哀はいつもと変わらぬ声で答えた。が、疲れているのか、どことなく足取りが頼りない。
「なあ、その荷物、重いんじゃないのか?」
「平気………」
「つったって、ふらついてるじゃねえか。貸せよ」
言って、京平は哀の持っていたショルダーバッグを脇から掬い上げた。
さっきから持つと言っているのだが、哀は遠慮しているのか持たせてくれないのだ。
軽い気持ちでバッグを肩にかけようとした瞬間、京平の腕ががくんと落ちる。
「な、なんだこれ……!」
なんて重さだ。女の持てる荷物じゃない。
この重量を姿勢も乱さずに運んでいた彼女に驚嘆する。
「なに入れてんだよ?! 尋常じゃないぞ、この重さっ!?」
「………各種退魔装備。咒符や手裏剣、苦無、螺旋鋲、繁藤弓。それに浄拭済みの斎鉈が二本。軽鎧や鉢鉄(はちがね)も入れている……。中でも一番重いのは………」
「も、もういいもういい! そんだけ聞きゃ分かるって」
さえぎって鞄を持ち直す。不意の重さにとまどったが、持てなくはない。
「…………。(海神って、実はヲタク気質なのか?)」
いつもは無口なクセに、何かの説明となれば途端に多弁になる。ヲタの基本だ。
「何……?」
「い、いや、なんでもねえ」
京平は誤魔化して歩調を早めた。
不思議と気分は落ち着いていた。彼女とならばきっと妹を助けられるだろう。そう信じることができた。
「なあ、海神。今回のことが全部片づいたらさ」
さざめく雨声だけが夜道を充たす。夜が明ける気配はまだない。
足音はいつの間にか京平のものだけになっていた。
「………海神?」
哀の返事はなかった。代わりに、絹布が落ちるような、やけに軽い音がした。
振り返れば、くずおれた哀の肢体。
「お、おいっ!」
慌てて駆け戻り、哀を抱き起こす。彼女の肌は蒼白を通り越して土気色になっていた。
冷たい肌とは対照的に、じっとりと熱い感触。おびただしい量の血液が脇腹を中心に広がっていた。
こんな傷でどうやって今まで歩けていたのか。
「おいっ、海神、海神っ!」
哀は目を閉じたまま動かない。ただでさえ虚ろな彼女の命の灯火は、雨の下で消えかかっていた。
傷の程度が分からない以上、むやみに動かすわけにもいかない。耳元でわめいて意識の回復をはかるしかない。
「海神、起きろって! 海神っ!!」
「………聞こえてる」
哀は目を閉じたまま、ぽつりとつぶやいた。
「私は……平気。先に行って……。どこでもいい。日から身を隠せるところ……。夜が、明ける前に…………っ」
眉根をゆがませ、苦痛にあえぐ哀。彼女に死が迫っているのは明らかだった。
「あなたは………まだ、日の光に………耐えられない……」
「俺のことはいいんだ! そうだ、いま救急車を───」
「聞いて!!」
哀が怒鳴った。遅れてやってきた激痛に彼女は声にならない悲鳴を上げて、だがすぐにぎこちない微笑を浮かべてみせた。
「………たいした怪我じゃないの……傷が開いただけ……っ…………だから、行って……早く………もう雨が、もた、ない……」
息をすることすらままならなくなっても、哀は自分のことよりも他人(ひと)の身を案じてくる。
精神力だけで保っていた彼女の意識は刻一刻と遠くなり、低い体温は目に見えて下がっていく。
「なんで、だ……?」
ひざまずいたまま、京平は力なくうめいた。
───なぜ俺はこうも無力だ。
妹を奪われて、目の前の少女も見殺しにして。何もできない。どうすることもできない。
「俺は……どうしたら………。どうしろってんだよっ………!」
答えてくれる者はいない。雨音にののしりさえ掻き消される。
だけど、いつか誰かが言った。
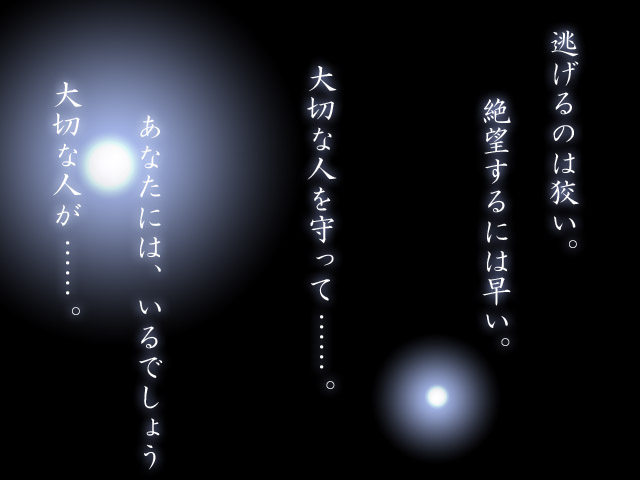
忘却の彼方より誰彼の声が響いた。忘れていた記憶が邂逅する。
大事な約束を思い出した。
───ここで終わるのか? 約束を破って逃げるのか?
「違う………!」
後悔に潰されるほど、俺は複雑にできていない。感傷に浸るような繊細さなど持ち合わせているものか。
そうだ。悔やむのは後でもできる。馬鹿が考えるほど無駄なことはない。目の前のことから一つ一つ片づけていけばいい。俺はそうやって生きてきたはずだ。
まずは彼女を助ける。いつだって何もできない事なんて無い。できることは絶対にある。
京平は一度目を閉じてうつむき、ゆっくりと開ける。
「………海神、ちょっと揺れるがこらえてくれ」
哀は弱々しい呼吸をしながらうなずいた。なるべく負担をかけないよう、細い体を抱き上げる。
それでも痛みが走るのか、哀は小さな痛哭を上げた。
しかし、構う余裕はない。この冷たい雨の下にいれば、彼女はますます弱っていく。
哀の言っていた“隠れ家”はすでに京平の網膜に透写されていた。五感あるいは六感すべてを統一させると、周囲の空間が歪み始める。
京平は鬼の力を使い、人を救った最初の鬼となった。高等妖術である“読心”と“幽界干渉”。その両方を、彼は鬼と化して一時間でやってのけてしまった。
鋼色の鬼は、夜の叢雲を飛び越える。
傷ついた少女を腕に抱え、病んだ紅藍の霞罹(かか)る朧月(つき)を全景に。
† † †
「まだ死ぬなよ、鬼遣」
鋼の腕に抱かれた少女をはるか眼下に捉え、駿足の鬼───捷疾鬼は叱咤した。
その姿は誰にも見えないが、捷疾鬼には全てが見えている。
予見とも言える何かを捷疾鬼は備えている。
「“そのとき”は来るさ。誰が動こうが、誰が望もうが。………いや、本当は誰も望んじゃいないのかも知れんがね」
苦笑し、かぶりを振って、捷疾鬼はくすんだ星空を見上げた。
「あんたはどう思う? 観たいかい、醒めない悪夢ってやつを」
銀河すら飛び越えた漆黒の闇に、彼女は訊ねた。
闇はただ、闇として、そこにあり続けた。